光ヨットが、光速の15%を達成するために必要な、初期の太陽中心からの半径
今回の『光ヨット』も、『恒星間 鮭の卵計画』と同じく、「恒星間飛行研究会」の活動中で検討された研究である。したがって、光速の15%で、αケンタウリに無人探査機を送り込む事の可否を中心に検討している。
光ヨットの最終到達速度は、初期状態の太陽中心からの距離と帆の面積と全体質量、及び帆の反射率・吸収率から比較的簡単な式で求める事ができる(付録の式(4)参照)。
光ヨットが、光速の15%を達成するために必要な、初期の太陽中心からの半径と帆の単位面積当りの質量
の関係を図1に示す。(計算簡略化の為、反射率100%、吸収率0%としている)
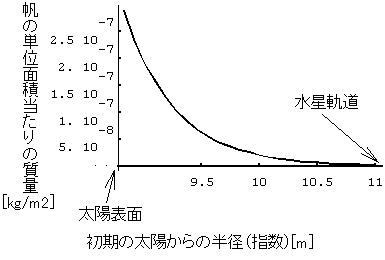
図1からも判るように帆の単位面積当りの質量は程度が必要である。この時、初期の太陽中心からの半径は、太陽半径の3倍である。つまり、太陽表面からは、太陽直径一個分しか離れていない。
単位面積当りの質量を満たす帆の厚さは、材料にアルミニュームと用いると、
つまり37pmになる。これは、アルミニュームの原子1個当たりの大きさ
つまり200pmよりも小さい(脚注1)。
直感的には、原子の大きさよりも薄い帆を作る事は不可能のようにも思えるが、37pmの厚さは平均の物であり、要は光を通さず、反射する軽い帆を作れば良い。帆を、光の波長以下の網で作ると軽量化は可能である。この時、網の格子間隔を500nmとしたとき、網の厚さ及び格子の幅は、3nmになる(脚注2)。この場合、透過率と反射率の劣化はまぬがれないであろう。
この時の運動を図2及び3に示す。また、加速度の変化を図4に示す。最大加速度はになる。
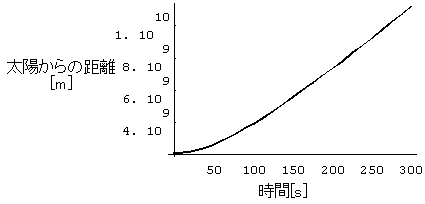
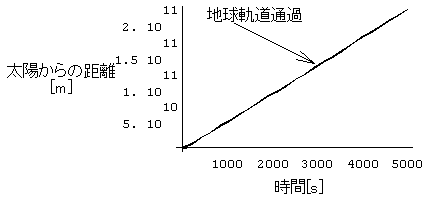
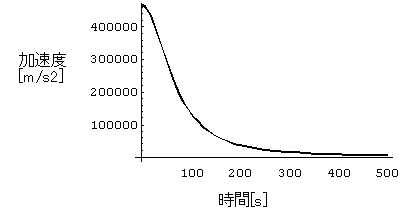
前述のような検討から、光ヨットで恒星間飛行を行なうには次のような問題点があげられる。
次に、各々について、検討する。
光速の15%を諦めると言う方法も考えられる。最終到達速度と帆の単位体積当たりの質量の二乗は反比例する。
仮に、光速の0.5%までの加速では、帆の厚さはむくのアルミニュームでも40nmになる。これは技術的に製造可能なものだ。しかし、αケンタウリに到着するのに860年もかかってしまう。これでは、誰も結果を見ることはできない。個人的に自分が成果を見られないような探査機は嫌だ。
アルミが最良の帆の材料とは限らない。そう言えば、現実にある非常に薄い金属箔の例として、加賀職人の打った金箔を買ったなあ。買っただけで、質量・反射率・吸収率の測定をしようとして、そのままになっている。あの金箔どうしたかなあ。
光ヨットは、余程ペイロードが軽い場合か、巨大な薄い帆を作れる技術的革新が無い限り、光速の15%よりも、ずっと低い速度で使用するべきだろう。
太陽光では無く、人工の光源を用いる方法も検討した。この場合、拡散を防ぐ為に、位相を合わせた単一波長の光(早い話がレーザー光)を用いる。この検討は、本来レーザー推進担当のT.A氏にやってもらったため、資料が手元に無いのだが、たしか、地球をも、吹き飛ばせるほどのレーザー大砲が必要と言う結論だった(T.Aさん、資料が電子化されていたら送って欲しい)。
SFに使うネタとしては、「非常に薄くて、耐熱性のある金属または合金等の材料が発見された」とか「ナノ・マシンが実用になった」と言う事で良いかもしれないが、現実的な恒星間探査計画を考えた場合、問題点が多い。
これら問題点や課題は、極めて解決困難ではあるが、光ヨットによる恒星間飛行は、理論的には決して不可能ではない。
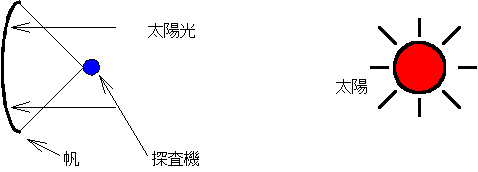
帆の面積を、反射率を
、透過率をp、光のエネルギーを
とする場合、探査機の受ける力
は次の式で、示される。
・・・・(1)
運動方程式は次の様になる。但し、ここではニュートン力学領域で方程式を立てている。
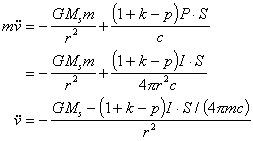
但し、は重力定数、
は太陽質量で
であり、Iは太陽の光エネルギーの総量で
、探査機の質量を
である。
式(2)は比較的簡単に解け、式(3)となる。
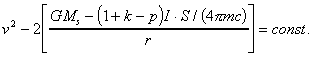
従って、光ヨットの最終到達速度は、初期速度
、初期の太陽からの半径
とした場合に式(4)の様になる。
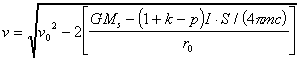
(4)式を用いて、最終到達速度を達成するために必要な、初期の太陽からの半径
と帆の単位面積当りの質量
の関係を(5)式に示す。
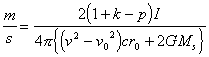
図1では、vを光速の15%とし、反射率、透過率p=0で、初期速度は、ほとんど影響が無いので
として計算している。
なお、ここまでの計算は、ヨットの帆を太陽光線に必ず垂直にするとしている。実際には、初期速度が、太陽光と並行でない限りは、ヨットの帆を太陽光線に垂直にすることは最適な制御ではない。
しかし、最終到達速度が光速の15%と、初期速度より遥かに大きい場合、その効果は非常に小さいと予想されるのと、上記の式のように簡単な解析解が得られないので、今回は無視した。
だが、最終到達速度が低い場合、ヨットの角度の最適化は無視できなくなる。検討には、コンピュータ・シミュレーションが必要になってくると思うが、どうすれば最適な制御か、また、どの程度の効果があるのか、見当も付かないので面白い研究課題になりそうだ。